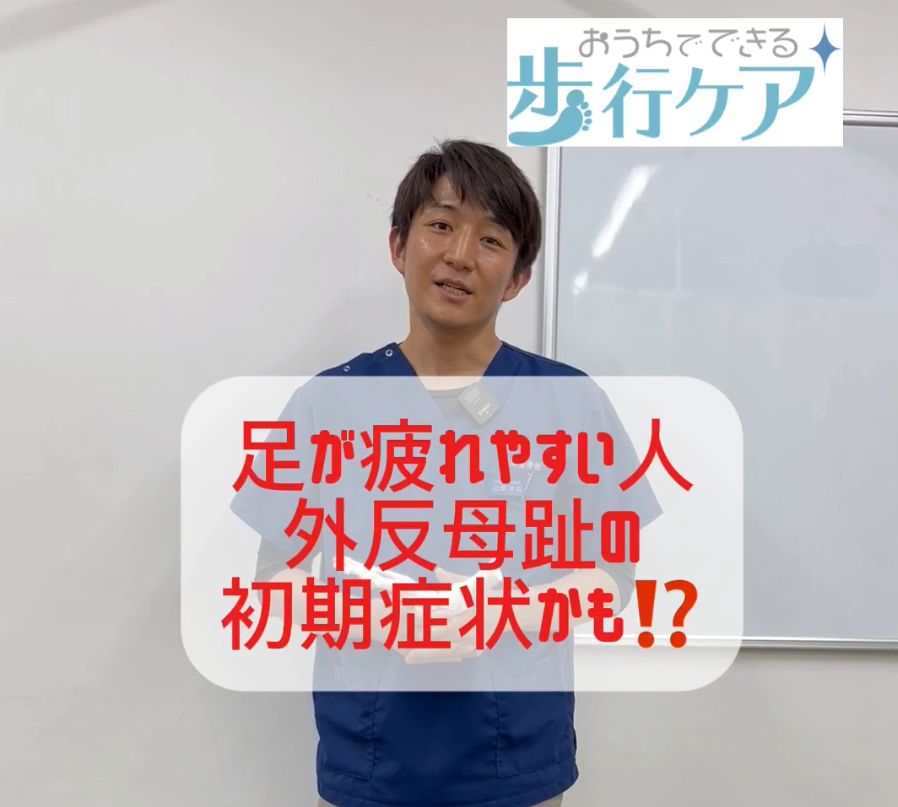こんにちは。
おうちでできる歩行ケア、代表の山岡です。
「最近、なんだか足が疲れやすい」「長く歩くと、土踏まずのあたりがだるくなる」「夕方になると足が重く感じる」そんなお悩みはありませんか?
実はその症状、ただの”疲れ”ではなく、外反母趾の初期サインかもしれません。
現代社会では、デスクワークの増加や運動不足により、足の筋力が低下している方が非常に多くなっています。
特に在宅勤務が増えた昨今、足を使う機会が減り、知らず知らずのうちに足の機能が低下しているケースが目立ちます。
今回は、足の疲れやすさと外反母趾の意外な関係について、そして自宅でできるセルフチェック方法を詳しくご紹介します。
記事の最後に動画でも解説しています。
そちらもご参考くださいませ。
足の疲れやすさと外反母趾の意外な関係
足が疲れやすい方の多くに見られるのが、足のアーチ(土踏まず)の低下です。
このアーチは本来、歩くときに体重を分散してくれる”クッション”の役割をしています。
人間の足には、内側縦アーチ(いわゆる土踏まず)、外側縦アーチ、横アーチという3つのアーチがあり、これらが協力して体重を支えています。
ところが、運動不足や加齢、長時間の立ち仕事などによってアーチが潰れてしまうと、足裏全体に負担がかかるようになります。すると、体のバランスを保とうとして、次第に親指が内側に引っ張られる形で外反母趾が進行していくのです。
つまり、足の疲れはアーチの崩れ=外反母趾のはじまりかもしれないというわけです。
多くの患者さんを診てきた経験上、「足が疲れやすくなった」「靴を履いていても疲れる」「歩くのが億劫になった」と感じ始めた時期が、実は外反母趾の初期段階だったということがよくあります。
なぜアーチが崩れるのか?
現代人のアーチが崩れやすい理由として、以下のような要因があります:
生活習慣の変化
– 歩く機会の減少
– 平坦な道ばかり歩くようになった
– クッション性の高い靴に慣れすぎた
筋力の低下
– 足の指を使わない歩き方
– 足裏の筋肉(足底筋群)の衰え
– ふくらはぎの筋力低下
体重や姿勢の問題
– 体重増加による足への過度な負担
– 前かがみの姿勢による重心の変化
これらの要因が重なることで、足のアーチが徐々に低下し、やがて外反母趾へとつながっていくのです。
外反母趾の初期症状をセルフチェック
では実際に、ご自身の足が外反母趾になりかけていないかをチェックしてみましょう。以下の項目を順番に確認してください。
チェック①:足の指がしっかり曲がるか?
まず、椅子に座った状態で裸足になってください。足の指を1本ずつ、ゆっくりと曲げてみましょう。
チェックポイント
– 人差し指から小指にかけて、スムーズに曲がるか
– 指の付け根(MP関節)からしっかり曲げられるか
– 曲げる際に痛みや違和感がないか
特に人差し指から小指にかけて、スムーズに曲がらない場合は要注意です。足の指が浮いてしまって地面につかない状態、いわゆる「浮き指」になっている可能性があります。
この浮き指の状態では、指がしっかりと体重を支えられず、重心が後ろに移動してしまいます。その結果、アーチも崩れやすくなってしまうのです。
もし指先だけでしか曲げられていない感覚があれば、指の付け根からしっかりと曲げるような練習を始めていきましょう。1日に数回、各指を10回ずつ曲げる練習から始めてみてください。
チェック②:片足立ちで7秒キープできるか?
次に、胸に手を当てた状態で、片足で立ってみましょう。7秒間ぐらつかずに安定して立てるかがポイントです。
実施方法
1. 壁から少し離れた安全な場所で行う
2. 胸の前で手を組む
3. 片足を軽く上げ、もう片方の足で立つ
4. 7秒間、できるだけぐらつかずに維持する
5. 左右両方で実施する
このバランスチェックでは、土踏まずがしっかり機能しているかが試されます。グラグラしてしまったり、すぐに足を下ろしたくなるような状態は、アーチが低下して足が支えきれなくなっているサインです。
また、左右差がある場合も要注意。片方だけバランスが取りにくい場合は、その足のアーチ機能が特に低下している可能性があります。
チェック③:足裏の感覚をチェック
足裏全体を床につけて立った時の感覚も重要な手がかりです。
正常な状態
– 土踏まずの部分が適度に浮いている
– 足の指先と踵、親指の付け根の3点で体重を支えている感覚がある
– 左右のバランスが取れている
注意すべき状態
– 土踏まずの部分も床についている感覚がある
– 足裏全体で体重を支えている感じがする
– 重心が内側や外側に偏っている感覚がある
改善のための第一歩
もし上記のチェックで「当てはまるかも…」と感じたら、まず取り組みたいのが**足の指をしっかり曲げる運動**です。
基本的な指の運動
グー・チョキ・パー運動
1. 足の指で「グー」を作る(指を丸める)
2. 「チョキ」を作る(親指を上、他の指を下に)
3. 「パー」を作る(指を大きく広げる)
4. これを10回繰り返す
タオル掴み運動
1. 床にタオルを敷く
2. 足の指だけでタオルを掴んで手前に引き寄せる
3. 左右の足で各10回実施
この運動は、足の裏の筋肉を目覚めさせ、アーチを引き上げる助けになります。左右両足でまんべんなく行うことで、片足立ちのバランスも安定してきます。
効果には個人差があり、症状が進行している場合は専門家への相談も検討してください。
日常生活で気をつけるポイント
外反母趾の予防や改善のために、日常生活でも以下の点に注意しましょう。
歩き方の改善
つま先を使った歩行
– 歩く際は足の指で地面を蹴るように意識する
– かかとから着地し、足の指まで重心を移動させる
– 小幅でも良いので、しっかりと足を使って歩く
靴選びのポイント
避けるべき靴
– ヒールの高い靴
– つま先が細すぎる靴
– サイズが合わない靴
動画で詳しく解説しています
こちらの動画では、より詳しいセルフチェック方法と、具体的な改善エクササイズをご紹介しています:
動画では、実際の指の動かし方や、正しいバランスチェックの方法を視覚的に確認できます。ぜひ実際の動作を確認しながら、ご自身の足の状態をチェックしてみてください。
また、動画で紹介しているエクササイズは、毎日短時間で行えるものばかりです。継続することで、足の機能改善が期待できますので、ぜひ習慣として取り入れてみてください。
歩行ケアプロソックスとの併用もおすすめ
株式会社サンヒルズの「歩行ケアプロソックス」は、こうした足のアーチの崩れを補助するために設計されています。

歩行ケアプロソックスの特徴
– デスクワーク中の足のサポート
– ウォーキングやジョギング時
– 長時間の立ち仕事での疲労軽減
– 旅行などの長距離歩行時
外反母趾が気になる方、足が疲れやすいと感じる方、予防に取り組みたい方には、ぜひ試していただきたい一足です。
サンヒルズの開発コンセプト
現在、株式会社サンヒルズではプロジェクト歩行ケアというものを立ち上げています。
全国からたくさんのご質問を日々いただいています。ですが直接治療ができるわけではないので、改善に結びつきにくいもどかしさがありました。
そこで、自宅でできる方法は何かないかと考えた結果、こちらの歩行ケアプロソックスを開発しました。多くの方に手軽に足のケアを実践していただけるよう、専門性と使いやすさを両立させた商品となっています。
=========================================
商品に関するお問い合わせや。ご質問等ありましたらいつでもご連絡くださいませ。